こんにちは。ひろろです。
午後のNo,2~5の選択問題、何を選ぶのかとっても迷いますよね。
専門的な内容にかなり分かれていくので、あまりにもわからない分野は手を出しにくい。そう思ったのは私だけでしょうか。
午前+午後の必須問題でなるべく点を取ったほうがいいのはわかっているけど、そう上手くはいかないものです。実際筆者も、午前の問題が思ったよりも解けなかったりなんかして、午前の試験終了時点でものすごく落ち込みました。
そうなると、もう午後で少しのミスも許されないですよね。

午前の対策ばかりに夢中になりがちですが、絶対に午後の対策をあきらめてはいけません。
今回は、午後で挽回して合格したといっても過言ではない私が、何を基準に午後の選択問題を選んだかをお伝えしたいと思います。
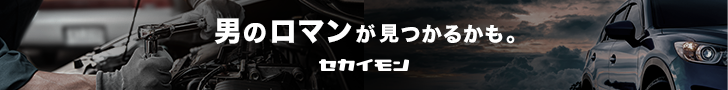
1 選択問題 種類の概要
初めてこの試験を受ける方のために、まずはここから確認していきましょう。
①No,2 測地測量に関する問題
公共測量における基準点測量の方法、点検方法等、工程の流れをきちんと理解しておくことに加え、セナダイナミック法等の計算問題が含まれます。
路線図の決定のような実務経験がないと理解しにくい問題や、行列や最確値に関する計算があるので、少し難しく感じる人も多いと思います。
②No,3 測図測量の問題
デジタル航空カメラ、地上レーザースキャナ、UAV等、近年の測量法について出題されます。
③No,4 地図編集 GIS
地図の種類と特徴の理解、座標計算や、GIS、メタデータといった分野が入ってきます。
④No,5 応用測量
路線測量と河川測量、土量計算が入ってきます。数学の計算問題が多いのが特徴です。
2,それぞれの特徴と分析
①No,2 測地測量に関する問題
作業の流れを掴み、実務の際に測量士として何を問われるのかを理解するといいと思います。
例えば、作業計画を立てること、測量結果が何に基づいていて、どれだけ正確な値に近づけることができるかなどです。そこから派生する問題が見受けられます。
難しい計算問題が多い印象ですが、あまりに高度な公式(例えばバイリニア補間法を使いなさいといったもの)は公式を問題に載せてくれてあるので、午前の計算問題をきちんと理解している人には計算問題と言われても、さほど問題ない程度だと思います。
近年大きな地震等で地形が変わってしまったという内容を耳にしたかもしれません。筆者は測量会社に勤めているわけではないので、測量士という仕事が何を意味するのか分からなかった部分もありましたが、この問題を理解しようと調べたときに、そういう復旧作業の最初に失われてしまった基準点の設置や、電子基準点がどこが有効で、正確な国土を再び算出する際にこのような作業内容を測量で行われていたのかと感動した記憶があります。
②No,3 測図測量の問題
筆者はこの分野は割と変動があるんじゃないかなと思っています。
最新の改正をチェックする必要があると思います。過去問ばかり対策として勉強した方には穴ができやすいかも。
測量を仕事でしている人たちには割となじみの多い単語もあると思いますが、実際に仕事をしていない人は、何が今主流で、何がすでにあまり使われていないのか、そして似通った名前の測量法があるので、どっちのことを言っているのか混乱しやすいかもしれません。(UAVレーザー測量とUAV写真点群測量など)
しかし、ここでは比較的(筆者の主観が入りますが)計算問題としてはそんなに難しくないかなと思います。種類、特徴、値など、少し混乱しやすい部分が多いですが、暗記が得意な方はいいと思います。
③No,4 地図編集 GIS
地図の種類の理解そして座標計算ありますが、ここは計算のパターンさえ覚えれば、そんなに難しくないので、わりと選ぶ方も多いのではないでしょうか。
日頃地図をよく見る方、スマホでナビ使うよなんて方はイメージしやすいと思います。
でも、JPGIS(地理情報プロファイル)などの専門性の高い内容も含まれているので、表にしたりして覚える内容も多々あるので、ご注意を。
④No,5 応用測量
路線測量、用地測量、河川測量は、私のように土木会社勤務であったり、土地家屋調査士を考えたことのある方はなじみがあるかもしれません。
この問題の大きな特徴はクロソイド計算等の計算問題ですが、公式もそんなに複雑ではないので、計算のパターンさえ覚えて、あとは正確な計算を心がければそんなに難しくありません。
午前の問題でも必ず路線測量の計算問題が出るので、解ければ点につながりやすい分野だと思います。
3、私はこれを選んだ
ここからは本当に私の個人的な見解です。私のように異種業から参入して資格をまず取りたいと考えている人は参考になさってください。私はNo,4と、No,5を選びました。
理由は、理解しやすいので、点につながりやすいと思ったからです。午後の大きな特徴は、単問ではなく、一連の流れによる問題です。
そのことを考えると、No,2は明らかに専門性が高すぎて、実際の業務についていないとイメージが付きづらく、計算問題も、もし理解が弱いところが出たら大きな失点につながるのではと感じ、避けました。
No,3は割と覚えるボリュームが多くて、過去問を解いていると、細かいところを突いた問題も出てました。覚える数字が混乱しやすいので、勘違いがあったら大きな失点になると思い避けました。
計算問題がそんなに難しくないので、自分としては好きな分野でしたが、点のために選ぶのはやめました。
No,4は割と身近でイメージしやすいので、応用もしやすく、点につながりやすいかなと考えて選択しました。覚えることと、計算のボリュームがバランスがいいかなというのが個人的な感想です。
No,5は自分の専門分野なので計算ミスが大きな失点になることはわかってましたが、ここはこの資格を取るからには挑戦したいと思いました。実際計算問題もパターンがあり、そんなに難しくないですし、覚える分野もそんなに多くないので、数学が得意な方は一番簡単な選択肢になると思います
4,まとめ
完全に個人的な見解と分析でしたがいかがだったでしょうか。
専門の方が見たら、と思いますが、実際に試験を受けた個人的な感想なのでお許しください。
何を選ぶかはもう、本当に自分がどの分野なら確実に点を取れるかってことにかかってきますが、何回か過去問を解いてみると、何となく自分の点の取れる分野がわかってくると思います。
点のためには、自分の好きな分野をあえて捨てることも必要になってくると思います。
そして、いろんな方が言ってますが、まずは午前の問題をまんべんなく解けるように、苦手分野をなるべく作らないようにしておくこと、お勧めします。
また、当日の試験は筆記になりますので、漢字で書けないなんてことが無いように、日頃から書いて解く習慣をつけるようにしましょう。そして、試験開始時に気がはやるあまり解答用紙の表紙に選択問題を何を選んだのか選択し忘れる、なんてことがないようにしましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
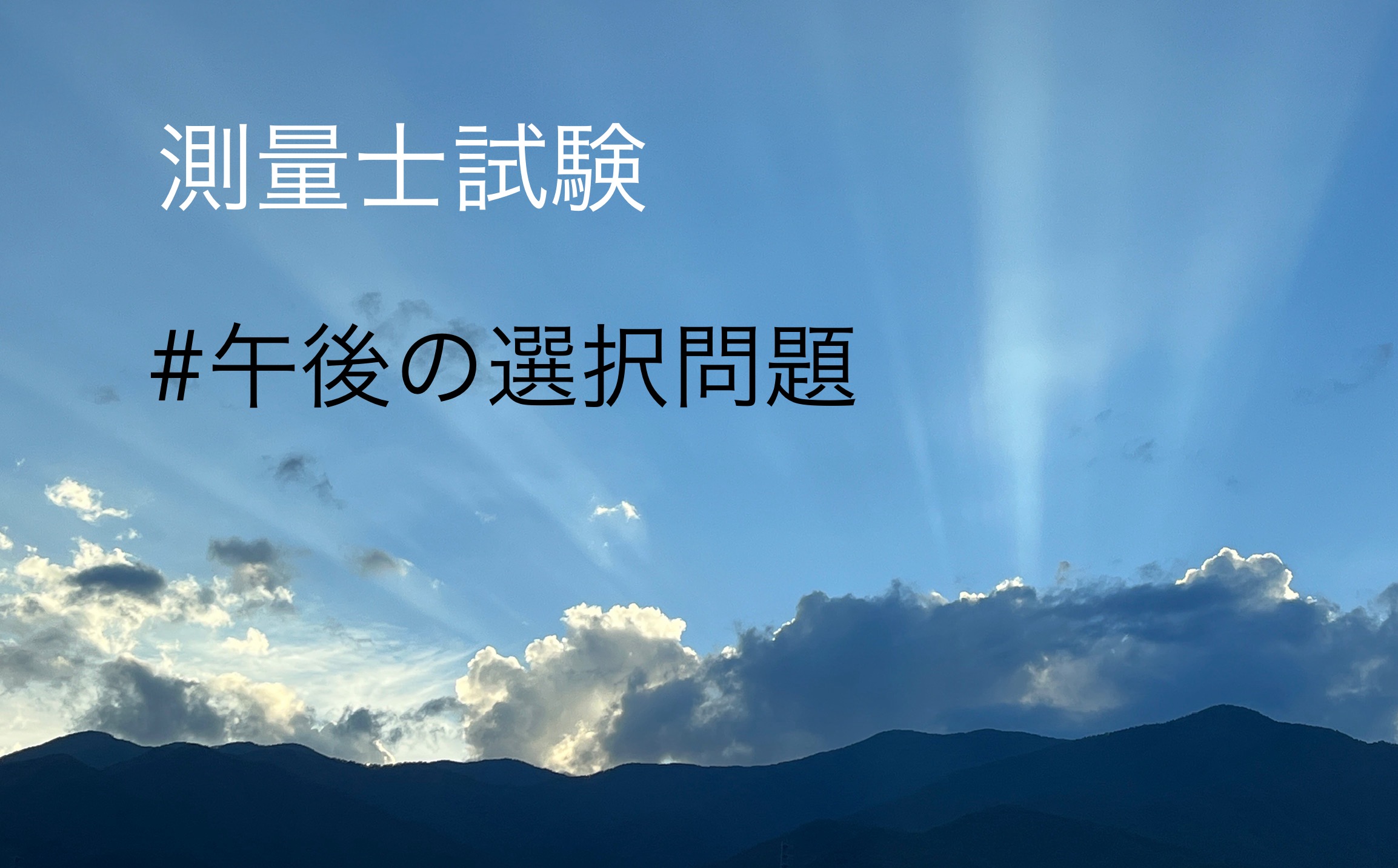

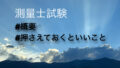
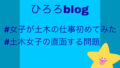
コメント